【卵アレルギーについて】症状・原因・対処法をやさしく整理
1. 卵アレルギーってどんなもの?
卵に含まれるたんぱく質がアレルゲンになる
卵アレルギーとは、卵を食べたときに体の免疫が過剰に反応してしまい、皮膚や消化器などにさまざまな症状が出る状態をいいます。
原因となるのは、卵に含まれるたんぱく質です。卵にはたくさんの種類のたんぱく質が含まれていますが、特に卵白に多い「オボムコイド」や「オボアルブミン」といった成分がアレルゲン(原因物質)になることが多いとされています。
子どもに多く見られるが、大人にも可能性あり
卵アレルギーは、乳児期・幼児期の子どもによく見られます。とくに離乳食を始めた時期に発症することが多く、食物アレルギーの中でも最も代表的なものの一つです。ただし、大人になってから突然発症することもあり、加齢や体調の変化にともなって敏感になるケースもあります。小さいころは平気だったのに、急に反応が出たという人も少なくありません。
2. 症状はどんなふうに出る?
皮膚の赤み・じんましん・口のまわりのかゆみなど
卵を摂取したあとすぐに、皮膚に変化が出ることがあります。代表的なのは、じんましんやかゆみ、特に口のまわりや顔に赤みが出る症状です。これらは軽度で済む場合も多いですが、繰り返すうちに反応が強くなるケースもあり注意が必要です。
嘔吐・下痢・呼吸困難など、全身に出ることも
一部の人では、消化器系の反応(腹痛・吐き気・下痢)や、呼吸器の症状(咳・ゼーゼーする・息苦しさ)が出ることもあります。症状が重い場合は「アナフィラキシー」と呼ばれる全身性の強い反応になることもあり、血圧の低下や意識の混濁といった危険な状態に進む可能性もあります。少量の摂取でも急激に悪化することがあるため、「今回は軽かったから大丈夫」と油断しないことが大切です。
3. 卵のどの部分が原因になるの?
卵白に多いオボムコイドという成分
卵アレルギーの大きな原因は、卵白に含まれる「オボムコイド」と呼ばれる成分です。これは非常に安定したたんぱく質で、加熱しても変性しにくいため、ゆで卵や卵焼きでもアレルギー反応を起こすことがあります。卵白は多くの料理で使われており、加熱後も残るこの成分が、敏感な人にとっては注意すべきポイントになります。
加熱しても反応が出るケースと出ないケース
人によっては、加熱した卵であれば症状が出にくいこともあります。たとえば、クッキーやスポンジケーキのように180℃以上で焼かれたものには反応しないけれど、ゆで卵やオムレツでは症状が出るというケースもあります。これは、加熱によってたんぱく質の形が変わり、体が異物と認識しなくなるためです。ただし、この違いは自己判断で見極めず、医師の指導のもとで確認する必要があります。
4. 卵アレルギーの人が気をつけるべき食べ物とは?
① 卵そのもの(ゆで卵・目玉焼き・卵焼きなど)
卵そのものを使った料理は、当然ながら避ける必要があります。全卵・卵白・卵黄いずれも注意が必要で、「黄身だけならOK」というケースもありますが、完全に分離していない限りリスクが残ります。半熟や生に近い状態のものは特に反応が出やすくなります。
② 卵が使われやすい加工品(パン・ケーキ・クッキーなど)
パンやケーキ、マフィン、プリン、シュークリームなど、卵が「生地」に混ぜ込まれて使われる製品は非常に多くあります。特に市販の焼き菓子類は、見た目にわかりにくいものも多いため、原材料表示をしっかり確認する習慣が大切です。
③ 見落としやすい原材料(マヨネーズ・ドレッシング・ハンバーグなど)
卵は調味料や総菜にもよく使われます。たとえば、マヨネーズやタルタルソースは卵黄が主成分ですし、ハンバーグやつくねなどは「つなぎ」として卵を加えるのが一般的です。ドレッシングにも卵を使ったものがあるため、油断できません。
④ 外食や総菜に含まれる「つなぎ」「衣」「ソース」への注意
外食やお惣菜では、料理の「衣」「ソース」「バインダー(結着剤)」として卵が使われている場合があります。たとえば、カツやフライの衣の卵、小鉢の和え物に使われるマヨネーズ、茶碗蒸し、オムライスなどが代表的です。また、サンドイッチの中身やドレッシング類も要注意です。
⑤ 加水分解卵白・卵黄レシチンなど、表示で気づきにくい卵由来成分
食品表示では、卵が「卵」とは書かれずに「加水分解卵白」「卵黄レシチン」「卵白リゾチーム」といった名前で使われることがあります。たとえば、加工ハムやアイスクリームなどに使われていることもあり、初めて見る言葉でもアレルギー源の可能性があると意識しておくことが大切です。
⑥ その他:意外と見落としやすいもの
・茶碗蒸し、たまご豆腐、親子丼
・インスタントラーメンの「かやく」や粉末スープ
・冷凍食品(グラタン・ドリア・ハンバーグ)
・パン粉・天ぷら粉(卵入りのもの)
・バニラアイス、チョコレート菓子、クリームサンド系のお菓子
こうした商品にも卵が含まれることがあるため、初めて食べるものは必ず表示を確認しましょう。
5. 食べられる範囲の判断と段階的対応
しっかり加熱した卵はOK?段階的に確認する方法
最近では、医師の管理のもとで「少しずつ加熱した卵から試していく」段階的な解除が行われることもあります。たとえば、まずはクッキー → パンケーキ → 蒸しパン → ゆで卵の黄身 → 卵白…というように、段階を追って確認していく方法です。
医師の指導のもとで少量から試す「経口負荷試験」
経口負荷試験とは、病院でごく少量ずつ卵を食べさせて反応を見る検査です。医療スタッフがそばにいて、もし症状が出てもすぐに対応できる環境で行われるため、安全に「どこまで食べられるか」を確かめることができます。
6. 卵アレルギーとつきあう日常の工夫
誤食を防ぐための家庭でのポイント
家庭では、調理器具や保存容器を分ける、ラベルを貼って食材を明確にするなどの工夫が有効です。また、家族全体で情報を共有し、誤って卵入りのものを出してしまわないよう、買い物や調理の場面で確認を徹底しましょう。
外食・園・学校との連携と伝え方
園や学校では、アレルギー対応食の提供や除去食への対応が進んでいますが、対応は自治体や施設によって異なります。保護者からの連絡ノート、アレルギー指示書、医師の診断書などを活用し、確実に情報を伝えることが大切です。また、外食時には「卵アレルギーがある」とはっきり伝え、口頭だけでなくメニューやウェブサイトでの確認も役立ちます。


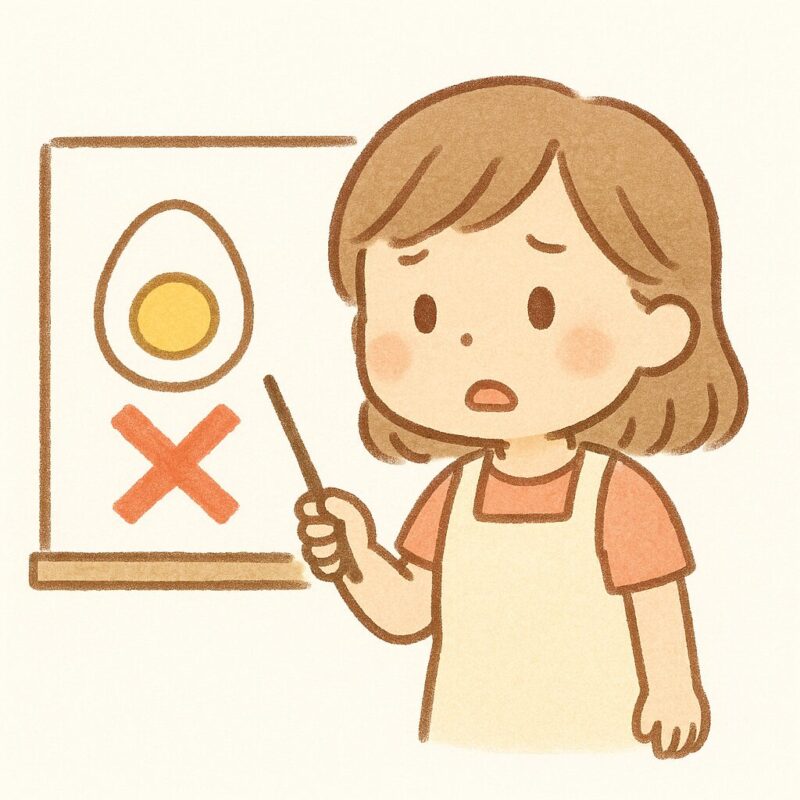

アレルギーについて】症状・原因・対処法をやさしく整理-120x85.jpg)