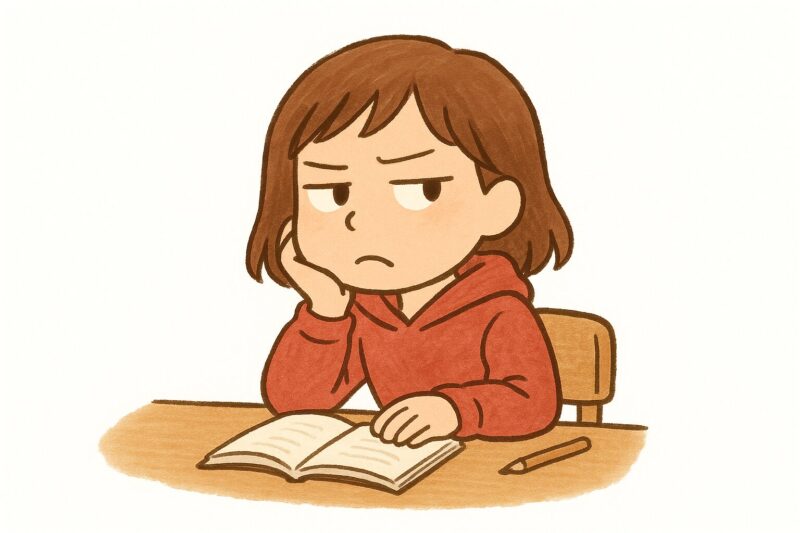「エリクソンの発達段階説」で見る思春期の“学びたくない”理由
「学びたくない」という感情はどこから来る?
勉強嫌いは意志の弱さなのか
「どうしてこの子はやる気がないんだろう?」と思春期の子どもを見て感じたことのある大人は多いでしょう。宿題を先延ばしにし、試験勉強にも本腰が入らない。だらだらと時間を過ごし、「勉強したくない」と言い切る姿に、もどかしさを覚える人もいるはずです。
でも、その背景には、単なる怠けや意志の弱さでは片づけられない、深い心理的な理由があるかもしれません。人の成長を心理的な発達段階から捉える「エリクソンの発達段階説」によれば、この“やる気のなさ”は、むしろ自然で必然的な過程と捉えることもできるのです。
思春期に特有の“反発”と“無気力”
思春期には、親や教師といった「教える側」への反発が強まり、「指示されること」そのものに嫌気が差すことがあります。同時に、何に対しても熱中できず、「何もしたくない」という無気力感にとらわれることも。こうした感情の揺れ動きは、思春期特有の心理的な課題に由来しています。
エリクソンの発達段階説とは
エリクソンという人物と理論の背景
エリク・H・エリクソン(1902–1994)は、ドイツ生まれの心理学者で、フロイトの精神分析をベースにしながらも、より社会的・文化的側面を重視した理論を展開しました。彼の理論の中核にあるのが「発達段階説」です。
この理論では、人生全体を8つの段階に分け、それぞれの時期において人が直面する“心理社会的課題”を明示しています。人はこの課題を乗り越えることで成長し、乗り越えられなければ課題が未解決のまま次の段階に進むことになる、という考え方です。
発達課題と「社会との関係性」の視点
エリクソンの発達段階説がユニークなのは、「個人の内面」と「社会との関係性」のバランスを重視している点です。たとえば、「自律性」や「勤勉さ」といったキーワードは、単に自己成長の問題ではなく、他者との関係や社会の中でどう振る舞うかと密接に関わっています。
発達段階8つの全体像(表付き解説)
以下が、エリクソンが提唱した8つの発達段階と、それぞれの時期に現れる心理社会的課題です。
| 段階 | 年齢期 | 課題(対立軸) | キーワード |
|---|---|---|---|
| 第1段階 | 乳児期(0〜1歳半) | 基本的信頼 vs 不信 | 愛着・安心感 |
| 第2段階 | 幼児期(1歳半〜3歳) | 自律性 vs 恥・疑惑 | 自立心・自己選択 |
| 第3段階 | 遊戯期(3〜6歳) | 自主性 vs 罪悪感 | 行動の主体性 |
| 第4段階 | 学童期(6〜12歳) | 勤勉性 vs 劣等感 | 努力と達成感 |
| 第5段階 | 青年期(12〜18歳) | 同一性(アイデンティティ) vs 同一性の拡散 | 「私は誰か」の模索 |
| 第6段階 | 初期成人期(20代〜30代) | 親密性 vs 孤独 | 対等な人間関係 |
| 第7段階 | 壮年期(40代〜60代) | 生殖性 vs 停滞 | 次世代との関わり |
| 第8段階 | 老年期(60代以降) | 統合性 vs 絶望 | 人生の振り返りと受容 |
このうち、本記事で焦点を当てるのは「第5段階:青年期」の領域です。
思春期にあたる「第5段階:同一性 vs 同一性拡散」
「私は誰か?」という問いの始まり
青年期は、「私は誰なのか」「どんな人生を送りたいのか」といった根源的な問いが強く意識される時期です。この問いに対し、納得のいく答えを見つけることが「同一性(アイデンティティ)の確立」と呼ばれます。
学びよりも“自分探し”が優先される時期
この段階では、内省や模索が主なテーマとなるため、学校での「学び」は後回しになりがちです。自分が何者であるかが定まらないうちは、学ぶこと自体に意味を見いだしにくいという心理的背景があります。
なぜこの時期に“勉強への意味づけ”が揺らぐのか
他人の期待と自分の内面のあいだで揺れる
親や教師は「将来のために勉強しなさい」と説きますが、本人は「その将来がそもそも見えない」状態にあります。自分の将来像が不明瞭なまま、「勉強=目的」という図式に納得できず、学びが遠く感じられるのです。
学ぶことが「自分ごと」にならない理由
義務感や周囲の評価のために勉強していると、それは「他人の物語」になってしまいます。「自分がこれを学びたい」と思えるようになるには、内面的な理由づけが必要です。しかし思春期はその“理由”が見つからない時期でもあります。
「学び」がアイデンティティと結びつかないとき
「将来のため」という言葉の空虚さ
「勉強すれば将来困らない」「いい大学に行けば安心」——こうした言葉は、アイデンティティが揺らいでいる青年期の心には響きにくいものです。「その将来は誰のものか?」「今の自分に本当に関係があるのか?」という疑問が優先されるからです。
学ぶ対象への無関心と疎外感
興味が持てない内容、形式的な授業、他者との比較ばかりが強調される環境では、「自分は学ぶ場に属していない」という感覚が生まれます。これが“学びからの逃走”へとつながることもあります。
周囲の期待がプレッシャーに変わる瞬間
大人の「正論」が反発を生む構造
「今頑張らないと後悔するよ」という正論は、時に若者を追い詰めます。彼らはその言葉の“正しさ”よりも、「自分の状況をわかってもらえていない」という感覚に反応します。正論が届かないのは、共感の地盤がないからです。
“やらされ感”が学びを拒む力に変わる
学びが自分の意思から発したものでないと感じた瞬間、人はそれを拒否するようになります。特に思春期は「自分で決めたい」という欲求が強く、それを奪うような指導は逆効果になりやすいのです。
友人関係と承認欲求の優先順位
学力よりも「居場所」が重要になる
この時期の多くの子どもにとって、教科書の内容よりも大切なのは「友人関係」や「所属感」です。集団の中での位置づけや、誰かに受け入れられることが、アイデンティティの一部を形づくるからです。
周囲との比較が学習意欲に影を落とす
学校は常に「他者との比較」が存在する空間でもあります。テストの順位や評価が前面に出るほど、「自分には価値がない」という認識が強まり、学びからの距離が生まれることもあります。
“学ぶ意味”が見えたときの変化
偶然の出会いや成功体験の力
興味を引く本との出会い、あるいは小さな成功体験。そんな偶然がきっかけで、「学ぶって面白いかも」と感じる瞬間が訪れることがあります。これはアイデンティティの揺らぎの中で生まれる「自己との接続点」です。
「自分で選んだ」という感覚の影響
与えられた内容ではなく、「自分で選んだ」学びは強いです。学ぶ行為が自分の意思と重なったとき、そこには動機や意味が生まれます。思春期における学習意欲の鍵は、この“自分で決めた感覚”にあるのかもしれません。
発達段階に応じた関わり方とは
「理解されている」という感覚の大切さ
大人の役割は「正しく教える」ことではなく、「その迷いごと受け止める」ことかもしれません。本人の中で何が起きているのかを想像し、寄り添う姿勢が信頼関係を生みます。
説得より“対話”を重ねる姿勢
相手の言葉に耳を傾け、無理に答えを与えず、問いを共有する。こうした「対話」が、揺らぎの中にいる若者にとっての安心感や、自己肯定の種になります。
アイデンティティが定まった後に訪れる変化
第6段階(親密性)への移行と価値観の再構築
青年期を抜けた後、人は「他者との親密な関係」を築くことを課題とします。この時期にようやく、過去の学びや経験が自分の価値観として再構築され、学びの意味が取り戻されることもあります。
「遅れて始まる学び」の自然さ
思春期に「学べなかった」としても、それが取り返しのつかない失敗になるわけではありません。むしろ、後になって「学ぶとは何か」を理解することこそ、深い学びの始まりでもあるのです。
エリクソン理論の限界と補足的視点
文化や時代による違いへの配慮
エリクソンの理論は欧米文化圏をベースにしており、日本の教育環境や家族観とは異なる部分もあります。そのまま当てはめるのではなく、文化的文脈に応じた読み替えが必要です。
他の理論との組み合わせで見えるもの
ピアジェの認知発達理論や、ヴィゴツキーの社会文化理論など、他の視点と組み合わせることで、思春期の学びに対する理解はより立体的になります。エリクソンの理論は「一つの見方」であるという前提を忘れずに扱うことが大切です。
“学ばない”こともひとつの過程として
遠回りにも意味があるという視点
「学びたくない」という時期があっても、それは一過性のものであり、むしろ内面の葛藤や模索を通して、自分らしい学び方に出会うための通過点でもあります。遠回りに見えても、その時間は無駄ではありません。
一時的な停滞をどう受けとめるか
大切なのは、その停滞を“欠陥”として捉えないことです。成長のプロセスには揺らぎや沈黙の時間も含まれている。そう理解することで、若者の迷いや抵抗も、自然な発達の一部として見えてくるかもしれません。